はじめに
「うちの基幹システム、20年以上動いてるんですよね…」
もしあなたがこんな会話を社内で聞いたことがあるなら、今すぐこの記事を読んでください。
経済産業省の警告によると、レガシーシステムを放置した場合、2025年以降、日本全体で年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があります。しかも、2025年には21年以上稼働しているシステムが全体の6割を占めると予測されています。
つまり、「うちの会社は大丈夫」と思っていても、実は多くの企業が同じ危機に直面しているんです。
でも、大丈夫。まだ間に合います。この記事では、20代の製造業SEであるあなたが、経営層を動かして「2025年の崖」を回避するための具体的な方法をお伝えします。
2025年の崖とは?
2-1. 経産省が鳴らす警鐘
「2025年の崖」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは、経済産業省が2018年に発表したDXレポートで使われた表現で、レガシーシステム(老朽化した古いシステム)を放置すると、2025年以降、企業競争力の低下や経済的損失が急激に拡大する、という警告です。
経産省のDXレポートによると、レガシーシステムを放置することで、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性がある
さらに深刻なのは、システムの老朽化が加速している点です。
2025年には21年以上稼働しているレガシーシステムがシステム全体の6割を占めると予測されている
つまり、「うちだけじゃない」んです。日本中の多くの企業が、同じ問題を抱えています。
2-2. なぜ2025年なのか?
では、なぜ「2025年」なのでしょうか。
それは、この年が既存システムのサポートが終了し、ソフトウェア・ハードウェア・技術者が同時に失われるタイミングだからです。
2025年が既存の基幹システムのサポートが終了し、ソフト・ハード・技術者が失われるタイミング。この年を境に、レガシーシステムの維持がさらに困難になる
例えば、1950年代に開発されたプログラミング言語「COBOL」。古い言語であるがゆえに、対応できる技術者の多くは高齢者です。基本構造を理解した上で処理ができる技術者の数が減少する以上、企業は常に人材確保の問題に直面します。
2-3. 5つの深刻なリスク
レガシーシステムを放置すると、以下の5つのリスクが発生します。
1. システムのブラックボックス化
長年の改修により、全体像を把握できる人がいなくなります。
2. セキュリティリスクの増大
サポート終了により、セキュリティパッチが適用できず、サイバー攻撃のリスクが増大します。
3. システム障害による経済損失
独立行政法人の情報処理推進機構(IPA)の2016年調査によると、システム障害による経済的損失は国内企業1社当たり約2億1,900万円
4. 維持コストの増大
サポート終了後、高額な保守契約が必要になります。
5. DX推進の阻害
最新デジタル技術との連携が困難になり、新しいビジネスモデルへの対応ができなくなります。
製造業の現場で起きている3つの問題
では、製造業の現場では具体的にどんな問題が起きているのでしょうか。
実は、私が話を聞いた何社かの製造業では、驚くほど似た問題を抱えていました。あなたの会社にも当てはまるかもしれません。
問題1: システムのブラックボックス化
「このシステム、誰が作ったか分かる人いますか?」
こんな質問をしたとき、誰も答えられない。これが「ブラックボックス化」です。
長年の改修・追加開発により、システムの全体像を把握できる人がいない。ドキュメントが整備されていない。オリジナルの開発者が退職済み
例えば、ある製造業の会社では、20年前に導入した生産管理システムが今も動いています。でも、システムを理解している人は、60歳近い契約社員1名だけ。その人が退職したら、誰もシステムを直せなくなります。
予期せぬシステムエラー発生時、原因究明ができず、根本的な解決策が不明。一部改善しようとすると、他機能が動かなくなり、八方塞がりの状態に
怖いのは、「動いているから大丈夫」と思っていても、何かトラブルが起きたとき、誰も対応できないことです。
問題2: セキュリティリスクの増大
「Windows Server 2008、まだ使ってます」
もしあなたの会社でこんな状況なら、かなり危険です。
OSやソフトウェアのメーカーサポートが終了し、セキュリティパッチが適用できない。既知の脆弱性を抱えたまま運用
サポートが終了したシステムは、セキュリティパッチが提供されません。つまり、新しい脆弱性が見つかっても、対応できないんです。
サイバー攻撃のリスクが増大し、情報セキュリティの法令・ガイドラインを満たせず、コンプライアンス違反のリスクが発生。セキュリティ事故時、取引先や顧客からの信頼を大きく損なう
実際、ある中小製造業では、古いサーバーがランサムウェア攻撃を受け、顧客情報が流出しかけた事例があります。幸い大事には至りませんでしたが、取引先からの信頼は大きく揺らぎました。
問題3: システム障害による経済損失
「システムが止まったら、ラインも止まる」
これは製造業にとって、最も恐ろしい事態です。
独立行政法人の情報処理推進機構(IPA)の2016年調査によると、システム障害による経済的損失は国内企業1社当たり約2億1,900万円、国内全体では約4兆9,600億円
2億円以上の損失。これは決して他人事ではありません。
近年、基幹システム更新の過程で予期せぬ技術的問題が発生し、製造ラインの停止を余儀なくされたり、サービス停止により顧客にも影響が及ぶ事例が報告されている
ある金属加工業の会社では、生産管理システムのサーバーが突然ダウンし、3日間ラインが止まりました。その間の損失は、直接的な売上減少だけでなく、納期遅延による信用失墜も含めると、計り知れません。
しかも、老朽化したシステムは、修理する部品すら手に入らないことがあります。
老朽化したレガシーシステムのメーカーサポートが切れている場合、別途ベンダーと高額な保守契約を結ぶ必要がある。故障時の部品調達や修復に時間・金銭コストがかかり、その間のビジネス機会損失も考えると、維持費以上のコストがかさむ
出典: INES Solutions: レガシーシステムの課題
経営層を動かす解決策(3つの技術活用)
「2025年の崖」の問題は分かった。レガシーシステムを放置すれば、年間最大12兆円の損失。では、どうすればいいのか?
正直に言います。「完璧な解決策」はありません。でも、「現実的な解決策」はあります。
ここでは、20代の製造業SEであるあなたが、経営層を動かすための3つの技術活用戦略をお伝えします。重要なのは、「いきなり大規模投資」ではなく、「小さく始めて、効果を見せる」こと。これが経営層を動かす鍵です。
4-1. 解決策1: 生成AI活用でレガシーシステムを延命
「月額数千円」から始められる現実
「生成AI? うちには関係ない」
そう思っていませんか。実は、生成AIは「高価なもの」ではありません。
ChatGPTは無料版あり、有料版は月額$20(約3,000円)。Google Geminiも無料版あり、Advancedは月額$19.99(約3,000円)。Microsoft Copilotも無料版あり、Proは月額$20(約3,000円)
月額数千円。これなら、個人のポケットマネーでも試せます。
レガシーシステム保守での具体的活用
では、生成AIは具体的に何ができるのか。
1. レガシーコードの解析・ドキュメント化
20年前のCOBOLコード。
誰も読めない。。。
そんな時、生成AIにコードを読み込ませると、「このコードは何をしているか」を日本語で説明してくれます。
例えば、こんな感じです:
- 入力: 古いCOBOLコード
- 出力: 「このプログラムは、顧客マスタから住所データを抽出し、郵便番号で並び替えて、レポートを生成しています」
2. コードレビュー時間の大幅削減
生成AIの活用により、コードレビュー時間を約30-40%削減できるという報告があります
出典: 検索結果要約: 生成AI活用
コードレビューは、レガシーシステムの保守で最も時間がかかる作業の一つ。これが30-40%削減できれば、その時間を他の業務に回せます。
3. バグ検出精度の向上
人間だけでは見落とすバグも、生成AIは発見してくれることがあります。特に、複雑なロジックや、長時間のコードレビューで疲れているときに有効です。
成功事例: 生産性25%向上、作業時間92%短縮
具体的な成功事例を見てみましょう。
NECでは、生成AIに過去データを学習させ、工程FMEA(故障モード影響分析)を自動生成。生産性が25%向上(シミュレーション結果)
ミスミでは、3DデータをアップロードするだけでAIが自動見積。部品調達の作業時間を92%短縮
92%削減。これは驚異的な数字です。
補助金活用でさらに低コスト化
「それでも初期投資が…」という声が聞こえてきそうです。
大丈夫。補助金を活用すれば、初期コストを大幅に圧縮できます。
省力化投資補助金(最大50%)、IT導入補助金(最大75%)、人材開発支援助成金(最大75%)を組み合わせることで、キャッシュアウトを最大70%圧縮可能
つまり、100万円の投資なら、実質30万円で済む計算です。
注意点: 万能ではない
ただし、誤解しないでください。生成AIは万能ではありません。
AI倫理・品質保証の考え方、ハルシネーション(誤情報生成)への対策、人間のレビューが必須
生成AIは「補助ツール」です。最終的な判断は、人間が行う必要があります。
でも、月額数千円で試せるなら、試さない理由はありません。
4-2. 解決策2: IoTプラットフォームで段階的DX
「いきなり全工場」ではなく「1ライン」から
IoTと聞くと、「大掛かりな投資が必要」と思うかもしれません。
違います。小さく始められます。
小規模導入(5-10台規模): 数百万円〜。段階的投資により、初期コストを抑制可能
数百万円。これなら、経営層も「試してみよう」と言ってくれる可能性があります。
段階的導入の4フェーズ
IoTプラットフォームの導入は、段階的に進めるのが鉄則です。
フェーズ1: データ収集基盤の構築
- センサー設置
- データ蓄積
- まずは「データを集める」だけ
フェーズ2: 可視化
- ダッシュボード構築
- 現状把握
- 「今、何が起きているか」を見える化
フェーズ3: 分析・予測
- AI/機械学習の活用
- トレンド分析
- 「次に何が起きるか」を予測
フェーズ4: 自動化・最適化
- システム連携
- 自動制御
- 「自動で最適化」
重要なのは、「フェーズ1-2だけでも十分な効果がある」ということ。いきなりフェーズ4まで進む必要はありません。
導入効果: 稼働率10-15%向上、停止時間30%削減
では、実際にどれくらいの効果があるのか。
設備稼働率の可視化により、稼働率が平均10-15%向上。予知保全により、設備停止時間を30%削減
稼働率10-15%向上。これは大きいです。
例えば、1日8時間稼働の設備が、10%向上すれば、約48分多く稼働できます。年間にすると、約200時間。これは相当な生産量増加です。
スモールスタート: PoCから始める
「でも、本当に効果があるか分からない」
その不安、分かります。だからこそ、PoCです。
PoC(Proof of Concept)は、概念実証や実証実験。新しい概念・理論・アイデアを実際の開発に移す前に、実現可能性や効果を検証する工程
PoC成功の3つのポイント:
- 目的の明確化: 何を検証するのか
- 経営層との事前すり合わせ: 期待値を合わせる
- スモールスタート: 小規模から始める
DXを成功させるためには、中小企業においてはスモールスタートで成功事例を作り、徐々に範囲を拡大していくことがおすすめ
1ライン、1工程から始める。効果を測定する。成功したら、次のラインへ。これが正解です。
4-3. 解決策3: ERPパッケージで基盤刷新
ERP導入は「最後の手段」ではない
「ERP? うちには関係ない」
そう思っていませんか。確かに、ERP導入は大規模投資です。でも、「選択肢の一つ」として知っておく価値はあります。
製造業での導入効果: 在庫回転率15-25%向上
ERPを導入すると、どんな効果があるのか。
製造業でのERP導入により、在庫回転率が15-25%向上し、生産リードタイムが10-20%短縮されるという調査結果があります
具体的な効果:
| 効果カテゴリ | 測定指標 | 典型的な改善幅 |
|---|---|---|
| 在庫最適化 | 在庫回転率 | 15-25%向上 |
| 生産効率 | 生産リードタイム | 10-20%短縮 |
| 間接業務 | 事務作業時間 | 20-30%削減 |
| 意思決定 | 情報取得時間 | 30-50%短縮 |
特に、「情報取得時間30-50%短縮」は大きい。経営層が意思決定するとき、「データを集めるのに1週間」では遅すぎます。リアルタイムでデータが見られれば、意思決定のスピードが上がります。
投資対効果(ROI)の計算方法
「効果は分かった。でも、投資額は?」
その疑問、当然です。ここで、ROIの計算式を使います。
ROI (%) = (導入後の利益増加額 - 投資額) ÷ 投資額 × 100具体例:
- 投資額: 3,000万円
- 年間効果: 在庫削減500万円 + 生産性向上300万円 + 事務作業削減200万円 = 合計1,000万円/年
- ROI: (1,000万円 – 3,000万円) ÷ 3,000万円 × 100 = -66.7%(初年度)
- 投資回収期間: 3,000万円 ÷ 1,000万円 = 3年
投資回収期間の目安: 小規模ERP(従業員50名以下)2-3年、中規模ERP(従業員100-500名)3-5年
出典: 検索結果要約: ERP投資対効果
3年で回収。これなら、経営層も納得しやすいです。
段階的導入アプローチ: 全部を一度に入れない
「3,000万円も一度に投資できない」大丈夫。段階的に導入できます。
段階的導入の典型的なステップ:
まずは経理部門だけ
製造部門に拡大
生産計画と連携
全社統合
この方法なら、初期投資を抑えつつ、段階的に効果を確認できます。
見落としがちなコスト: 保守・運用・教育
ただし、注意点があります。
初期導入費用だけでなく、保守・運用費用、従業員の教育コスト、データ移行コスト、システム連携コストも考慮
出典: 検索結果要約: ERP投資対効果
見落としがちなコスト:
- 保守・運用費用: 年間投資額の15-20%
- 教育コスト: 従業員1人あたり10-20万円
- データ移行コスト: 投資額の10-15%
これらを含めて、トータルコストを計算する必要があります。
まとめ: 3つの技術を組み合わせる
生成AI、IoT、ERP。この3つは、それぞれ独立した解決策ではありません。組み合わせることで、より大きな効果を生みます。
例えば:
- 生成AIでレガシーシステムを延命しつつ
- IoTで現場のデータを収集・可視化し
- ERPで全社のデータを統合する
この組み合わせが、「2025年の崖」を回避する現実的な道筋です。
経営層への説明方法(実践編)
導入
技術は分かった。生成AI、IoT、ERPを活用すれば、レガシーシステムの問題は解決できる。
でも、最大の問題は「経営層をどう説得するか」ではないでしょうか。
正直に言います。技術の話をしても、経営層は動きません。経営層が動くのは、「投資対効果が明確なとき」です。
ここでは、20代SEのあなたが、経営層を動かすための実践的な説明方法をお伝えします。
ステップ1: 現状の問題をデータで示す
KKD経営からの脱却
「うちの基幹システム、そろそろ限界です」
こう言っても、経営層は動きません。なぜか。
従来の勘・経験・度胸の「KKD経営」では、説得力に欠け、「あの人が言っているから正しそう」と本質的でない意思決定になる傾向があり、周囲の納得を得るのが難しい
経営層も「感覚」で判断したくないんです。でも、データがないから、感覚で判断するしかない。
だから、あなたがデータを示す必要があります。
悪い例と良い例
悪い例:
- 「業務効率が悪いです」
- 「生産性が低いです」
- 「システムが古いです」
これでは、「どれくらい悪いのか」が分かりません。
良い例:
- 「顧客情報の更新・管理に月間50時間かかっています」
- 「既存顧客の継続購入率が前年比15%悪化しています」
- 「システム障害が年間12回発生し、その都度3時間のライン停止が発生しています」
数値化することで、説得力が増します。
できるだけ具体的に記載。数値データを活用(例: 「顧客情報管理に月間○○時間かかっている」)。誰が見ても分かる状態にする
ステップ2: 「あるべき姿」を描く
DXビジョンの策定
現状の問題を示したら、次は「あるべき姿」を描きます。
DXビジョンとは、DXによって何を実現し、どのような成功をもたらしたいのかといった、「あるべき姿」を思い描いた変革の御旗
ただし、注意点があります。
NG: 抽象的な表現
- 「AIを使って何かしよう」
- 「DXを推進します」
- 「デジタル化します」
これでは、経営層は判断できません。
OK: 具体的な表現
- 「在庫管理を自動化し、在庫回転率を20%向上させます」
- 「生産管理システムを刷新し、生産リードタイムを15%短縮します」
- 「IoTセンサーを導入し、設備稼働率を可視化します」
具体的に描くことで、経営層が判断しやすくなります。
単に「AIを使って何かしよう」というレベルでは、全社的な変革につながらない
ステップ3: 投資対効果を試算する
ROI計算式を使う
「あるべき姿」を描いたら、次は「投資対効果」を試算します。
ROI (%) = (導入後の利益増加額 - 投資額) ÷ 投資額 × 100この計算式を使って、具体的な数字を示します。
効果測定の実例: 年間57万円の削減
実際の事例を見てみましょう。
某金属加工業(従業員35名)の効果測定:
| 業務項目 | 導入前 | 導入後 | 削減効果 |
|---|---|---|---|
| 月次報告書作成 | 16時間 | 8時間 | 50%削減 |
| 見積書作成・管理 | 12時間 | 6時間 | 50%削減 |
| 経費精算処理 | 8時間 | 3時間 | 62.5%削減 |
| 合計 | 36時間 | 17時間 | 月間19時間削減 |
年間効果:
- 19時間 × 12ヶ月 = 228時間(約1.4人月相当)
- 金銭価値: 時給2,500円換算で年間57万円の人件費削減効果
57万円。これは小さい金額に見えるかもしれません。でも、35名規模の企業なら、十分な効果です。
重要なのは、「具体的な数字で示す」こと。これが経営層を動かします。
ステップ4: 提案書を作成する
無料テンプレートを活用
「提案書なんて作ったことない」
大丈夫。無料テンプレートがあります。
提案書の基本構成7項目:
- タイトル・件名
- 提案の背景・現状課題
- 提案内容・解決策
- 期待される効果・目標
- 費用・予算
- スケジュール・実施計画
- 添付資料
出典: ナレカン: 提案書テンプレート
無料テンプレート提供サイト:
- 才流(サイル): PowerPoint、記入例付き
- freee: Word、シンプルな稟議書
- DocTok: DX企画書専用
これらを活用すれば、1日で提案書を作成できます。
事前の根回しが重要
ただし、提案書を作るだけでは不十分です。
稟議書提出による”急な申し出”だけでは理解が得られず、承認が得られないケースがある。稟議書提出前に関係者へ事前説明、認識のズレを解消
事前の根回し。これが成功の鍵です。
根回しのポイント:
- 提案書提出の1-2週間前に、非公式に説明
- 経営層だけでなく、関係部署にも説明
- デモ・実演で具体的なメリットを見せる
まとめ: データで語る、具体的に描く、効果を試算する
経営層を動かすための3つのステップを振り返ります。
KKD経営からの脱却
数値化で説得力を高める
DXビジョンの策定
抽象的ではなく、具体的に
ROI計算式を使う
具体的な効果測定例を示す
この3つができれば、経営層は動きます。
「データで語る、具体的に描く、効果を試算する」
これが、経営層を動かす鍵です。
今すぐできるアクション(3ステップ)
では、理論は分かった。じゃあ、今日から何をすればいいのか?
そう思ったあなたに、具体的な3つのステップをお伝えします。いきなり大掛かりなシステム刷新を目指す必要はありません。まずは小さく、でも確実に始めることが大切です。
ステップ1: 業務の棚卸しから始める
まず最初にやるべきは、業務の見える化です。
DX推進に取り組む際、必ずやっておきたいのが現状の把握。自社のシステム状況、リソース、情報資産を可視化し、そのうえで「業務効率化」や「新しい価値創造」といった目的を設定します
出典: 見える化エンジンラボ: DX推進
具体的には、こんな作業です:
やること:
- 全業務をExcelにリストアップ
- 各業務の「担当者」「所要時間」「頻度」を記録
- 時間がかかっている業務を特定
- デジタル化すべき業務を選定
期間: 1-2週間
ツール: Excel/スプレッドシートで十分
実例で見てみましょう:
ある金属加工業(従業員35名)が業務の棚卸しを実施した結果、以下のような時間がかかっていることが判明しました
| 業務項目 | 月間時間 |
|---|---|
| 月次報告書作成 | 16時間 |
| 見積書作成・管理 | 12時間 |
| 経費精算処理 | 8時間 |
| 合計 | 36時間 |
この3つをデジタル化対象に選定し、次のステップへ進みました。
ポイントは、「完璧な棚卸し」を目指さないこと。まずは大まかに把握するだけでOKです。
業務名称、ドキュメント/システム名称等に整合性がないと、棚卸そのものが全部やり直しになる。最初に「共通言語化」を徹底し、曖昧な表現を避ける
ステップ2: 小規模PoCで試す
業務の棚卸しができたら、次は小さく試すフェーズです。
PoCは新規事業を成功に導くための手段であって目的ではない。何を検証したいのか、誰が最終判断するのかを明確にすることが成功の鍵
いきなり数百万円のシステムを導入する必要はありません。まずは無料版や低価格ツールで試してみるんです。
具体的な方法
① 生成AIで技術文書を検索
- ツール: ChatGPT無料版、Google Gemini
- 費用: 無料(有料版でも月額$20=約3,000円)
- やること:
- 過去の技術資料をPDF化
- ChatGPTに質問して回答精度を検証
- 「過去の不具合対応事例を教えて」など
- 期間: 2-3ヶ月
② 業務効率化ツールの試験導入
- ツール: Google Workspace、Slack、Notionなど
- 費用: 月額数千円〜
- やること:
- 1部署・1チームから開始
- 月次報告書をスプレッドシートで自動集計
- 効果を数値で測定
③ 低コストセンサーでIoT試行
- 初期投資: 10-50万円
- API利用料: 月数千円〜数万円
- やること:
- 1ライン・1工程から開始
- 稼働データを収集・可視化
- 異常検知の精度を検証
重要なのは、「効果を測定する」こと。
先ほどの金属加工業の例では、ツール導入後、以下のような効果が出ました。
| 業務項目 | 導入前 | 導入後 | 削減効果 |
|---|---|---|---|
| 月次報告書作成 | 16時間 | 8時間 | 50%削減 |
| 見積書作成・管理 | 12時間 | 6時間 | 50%削減 |
| 経費精算処理 | 8時間 | 3時間 | 62.5%削減 |
| 合計 | 36時間 | 17時間 | 月間19時間削減 |
年間効果: 19時間 × 12ヶ月 = 228時間(約1.4人月相当)
金銭価値: 時給2,500円換算で年間57万円の人件費削減効果
この数字があれば、経営層への説明がグッと楽になります。
ステップ3: 経営層へ提案する
PoCで効果が出たら、いよいよ経営層への提案です。
稟議書作成の際、現状の問題はできるだけ具体的に、数値データを活用して誰が見ても分かる状態にすることで、決裁者は意思決定しやすくなる
提案書の基本構成:
- 現状の課題(数値で示す)
- PoCの結果(効果を数値で示す)
- 本格導入の提案(費用と効果)
- ROI試算(投資回収期間)
- 補助金活用(初期投資の圧縮)
無料で使えるテンプレート:
- 才流(サイル): PowerPoint、記入例付き
- DocTok: DX企画書専用テンプレート
- freee: シンプルな稟議書テンプレート
出典: 才流: 稟議書テンプレート
補助金も活用しましょう:
省力化投資補助金 × IT導入補助金 × 人材開発支援助成金 を組み合わせることで、キャッシュアウトを最大70%圧縮可能
具体的な補助金(2025年):
- 省力化投資補助金: 最大50%補助
- IT導入補助金: 最大75%補助
- 人材開発支援助成金: 最大75%補助
これらを組み合わせれば、実質的な初期投資を大幅に抑えられます。
まとめ: 3ステップの全体像
ステップ1: 業務を見える化する(1-2週間)
ステップ2: 小さく試す(2-3ヶ月)
ステップ3: 数字で説得する(提案書作成)
いきなり完璧を目指さないこと。
まずは小さく始めて、成功体験を積み重ねることが、経営層を動かす最短ルートです。
まとめ
「2025年の崖」は、他人事ではありません。
経産省のDXレポートによると、レガシーシステムを放置した場合、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性がある
そして、2025年はもう目の前です。
この記事では、20代製造業SEのあなたが、経営層を動かして「2025年の崖」を回避するための具体的な方法をお伝えしました。
3つの重要ポイント:
1. 今すぐ行動する
「いつかやる」ではなく、「今日から始める」。業務の棚卸しは、Excelさえあれば今日からできます。
2. 小さく始める
いきなり数千万円のシステム刷新を目指す必要はありません。まずは無料版や月額数千円のツールで試してみる。成功体験を積み重ねることが、経営層の理解を得る近道です。
3. 数字で語る
従来の勘・経験・度胸の「KKD経営」では、周囲の納得を得るのが難しい。データや数値を用いた意思決定であれば、経営層も周囲も納得しやすくなる
PoCで効果を測定し、ROIを試算し、提案書を作成する。この3つがあれば、経営層は動きます。
20代のあなたには、まだ時間があります。
でも、その時間は無限ではありません。
ある製造業のベテラン技術者が退職し、その人しか分からないシステムが残される。セキュリティパッチが適用できないまま、ランサムウェア攻撃のリスクにさらされる。製造ラインが止まり、数億円の損失が発生する。
こんな事態を防げるのは、あなたです。
今日から、一歩を踏み出してください。
業務を見える化し、小さく試し、数字で説得する。
あなたの行動が、会社の未来を変えます。

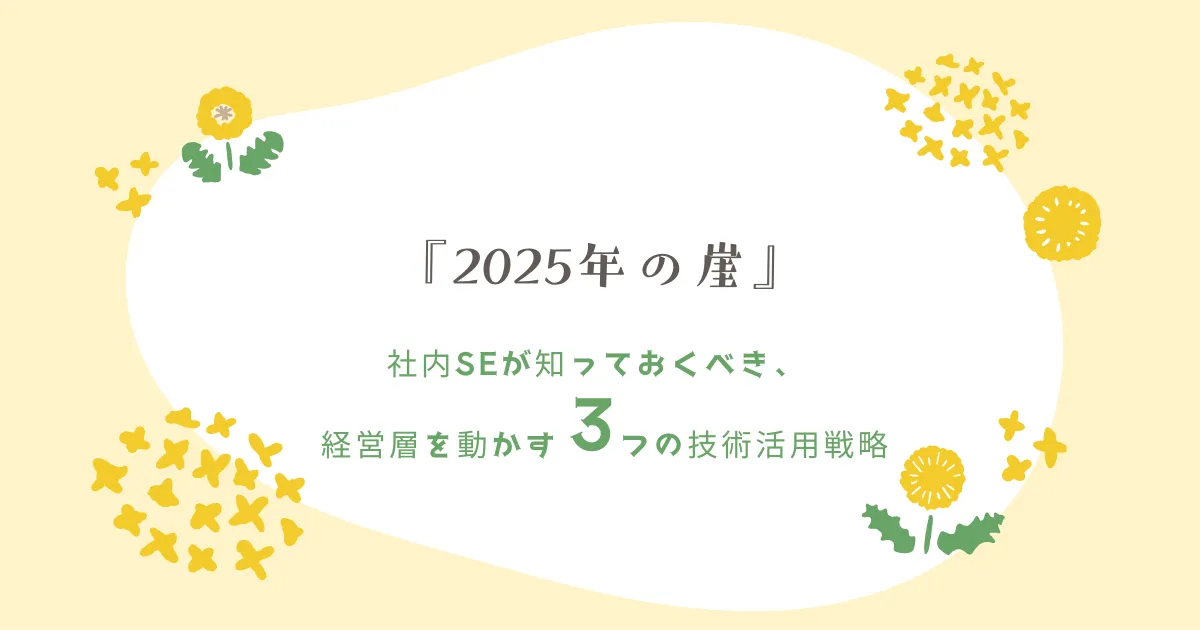

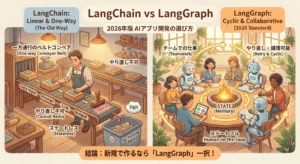

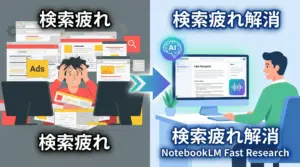
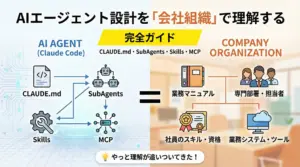


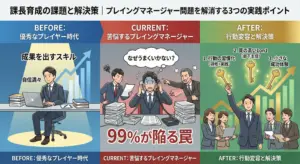

コメント