社会人になって数年経つと、いろんなニュースが「自分ごと」として見えてくるようになる。
2025年10月21日、高市早苗氏が日本初の女性総理大臣に就任した。ニュースを見て「おお、すごいな」と思った直後、こんな見出しが目に飛び込んできた。
「働いて働いて働いて働いて働く」「ワークライフバランスを捨てる」
正直、背筋が寒くなった。
特に、社会人1年目のあなた。まだ「仕事ってこういうものか」って掴みかけてる段階だよね。やりたいこともよくわからないし、漠然とした不安もある。「正直、仕事したくない」って思う日もあるだろう。
でも、今起きてることを知っておいた方がいい。
この記事では、2025年10月に起きている変化と、社会人1年目のあなたが「今すぐやるべきこと」について、本音で書いていく。
2025年10月、日本で何が起きてるの?
高市総理誕生と「ワークライフバランスを捨てる」発言
2025年10月21日、高市早苗氏が日本の第104代内閣総理大臣に就任した。
自民党の高市早苗総裁(64)は21日召集の臨時国会で第104代首相に指名された。女性の首相就任は初めて。
日本初の女性総理の誕生。歴史的な瞬間だ。
ただ、問題はその後だった。総裁選の勝利演説で、高市氏はこう発言した。
「全員に馬車馬のように働いていただく。自身もワークライフバランスという言葉を捨てる。働いて働いて働いて働いて、働いて、参ります」
「働いて」が5回。これは比喩ではなく、実際の発言だ。
この発言は各方面から批判を浴びた。
自民党の高市早苗総裁の「ワークライフバランスを捨てる」との発言が波紋を広げている。重責を担う「強い覚悟を感じた」との評価がある一方、働き方改革の逆行につながるとの懸念も喚起。
「総理自身の覚悟」として受け止める声もある。でも、問題はこの次だ。
労働時間規制の緩和検討って、具体的に何?
高市総理は就任直後、厚生労働大臣に対して労働時間規制の緩和検討を指示した。
高市早苗首相は21日、現行の労働時間規制の緩和検討を上野賢一郎厚生労働相らに指示した。新閣僚への指示書に「心身の健康維持と従業者の選択を前提」としつつ「働き方改革を推進するとともに、多様な働き方を踏まえたルール整備を図ることで、安心して働くことができる環境を整備する」と明示した。
「多様な働き方」「安心して働く環境」という言葉は聞こえがいい。でも、実質的には「労働時間規制を緩和する」という内容だ。
現在の法律では、残業時間は原則として月45時間、年360時間まで。特別な事情があっても月100時間未満、複数月平均で80時間以内と定められている。これが2019年の働き方改革関連法で導入されたルールだ。
時間外労働の上限規制は、働き方改革関連法で2019年4月から導入されたルールです。原則として、1か月に45時間、1年で360時間までしか残業できません。
この規制が緩和されれば、企業側はより長時間労働を求められるようになる可能性がある。
高市氏自身も、総裁選の論戦などで「働き方改革の行き過ぎの部分は確かに出てきている。いま一度、検証しなければいけない」と指摘。「心身の健康維持と人の選択を前提に、(規制を)少し緩和する方法がないか検討する」と踏み込んだ。
「働きたい人が働ける環境」というのは一理ある。でも、現実問題として、「働かされる環境」になる可能性も十分にある。
実は経済も不安定?株価急騰の裏側
労働規制の話だけでも十分に気がかりだが、実は経済状況もかなり不透明だ。
高市総理の就任後、株価が急上昇している。いわゆる「高市トレード」だ。
「10月6日午前の東京株式市場で、日経平均株価が大幅に続伸し一時4万7800円を上回った。4日、自民党の新総裁に高市早苗前経済安全保障相が選ばれた。積極的な財政出動や金融緩和を推し進めるとの思惑から、幅広い銘柄に買いが膨らんでいる。」
そして10月24日時点では、日経平均株価は49,299円。もう少しで5万円に到達する勢いだ。
「日経平均株価3日ぶり反発 終値は658円高の4万9299円」(2025年10月24日)
出典:日本経済新聞
一見すると景気が良さそうに見える。でも、この急激な上昇には警戒する声もある。
「債券市場では財政拡張への警戒感が強まり、償還期間の長い30年物国債利回りは最高記録を塗り替えた。」
債券市場は、株式市場よりも冷静だ。国債利回りが最高記録を更新しているということは、市場が「財政悪化のリスク」を織り込み始めているサインでもある。
さらに、政権基盤も不安定だ。自民党と日本維新の会の連立で、ギリギリ過半数を確保している状態。公明党は連立から離脱した。
「自民党は日本維新の会と連立政権樹立で合意しており、高市早苗総裁が衆院本会議の首相指名選挙で第104代首相に選出された。」
政権基盤が不安定だと、政策の継続性に疑問符がつく。株価が政策期待だけで上がっているとすれば、その期待が裏切られた時のリスクは大きい。
社会人1年目のあなたが、今感じている不安は正しい
「働きたくない」って思う自分を責めなくていい
社会人1年目だと、「仕事したくない」って思うこともあるよね。やりたいことがわからない、勉強も得意じゃない、帰宅後はゲーム実況見たりYouTube見たりしてダラダラ過ごしてる。
それ、全然悪いことじゃない。
ただ、今回のニュースを見て、「このままじゃまずいかも」って感じたなら、その直感は正しい。
会社が守ってくれる時代は、もう終わった
「会社に入れば安泰」という時代は、とっくに終わっている。
終身雇用は崩壊し、企業は利益のために人員を調整する。景気が悪化すれば、リストラもある。労働規制が緩和されれば、長時間労働を求められる可能性もある。
会社は、あなたを守ってくれない。
「このままじゃヤバい」と思う理由
冷静に考えて、今の状況はこういうことだ。
1. 労働時間規制が緩和される可能性 「働きたい人が働ける」という名目で、実質的には長時間労働が復活するかもしれない。「法律が変わったから」という理由で、今より多く働かされる可能性がある。
2. 経済の不透明感 株価は上がっているが、債券市場は警戒している。政権基盤も不安定。もし経済が調整局面に入れば、会社の業績も悪化し、ボーナスカットやリストラのリスクもある。
3. スキルがないと選択肢がない もし今の会社がヤバくなっても、スキルがなければ転職できない。「次の会社を選ぶ」という選択肢がない状態は、かなり危険だ。
この3つが重なると、マジでヤバい。
じゃあ、どうすればいい?答えは「自分のスキル」を身につけること
不安定な時代だからこそ、「会社に依存しない力」が必要
会社は守ってくれないかもしれない。政治も経済も不安定かもしれない。
でも、自分のスキルは誰にも奪えない資産になる。
スキルがあれば、こんなことができる。
1. 転職という選択肢を持てる 今の会社がヤバくなっても、スキルがあれば次の会社を選べる。「この会社しかない」じゃなくて、「次はどこにしようかな」って考えられる。これは精神的にめちゃくちゃ楽だ。
2. 副業で収入を増やせる 本業がヤバくなっても、副業で稼げる。月3万円でも、年間36万円。これがあるだけで、心の余裕が全然違う。
3. 給料アップの交渉ができる スキルがあれば、「他の会社からオファーもらってます」って言える。会社側も、スキルのある人材は手放したくない。給料交渉の武器になる。
要するに、スキルがあれば「選ぶ側」に回れる。
勉強が苦手でも大丈夫。今は「オンライン学習」がある
「でも、勉強苦手だし…」って思うかもしれない。
大丈夫。今は、オンラインで手軽に学べる時代だ。
特に「Udemy(ユーデミー)」っていうサービスが、社会人にめちゃくちゃ使いやすい。私自身も実際に使ってスキルを身につけてきたし、周りでも使ってる人が多い。
Udemyって何?社会人1年目でも使えるの?
Udemyの特徴:買い切り型で何度でも見れる
Udemyは、世界最大級のオンライン学習プラットフォームだ。
Udemyは世界で6,200万人以上のユーザーがおり、そのうち日本のユーザーは130万人以上になります。公開されているコース数は21万本以上にのぼり、世界最大級の規模です。
出典:エンジニアtype「【Udemyとは?】基本的な使い方から専門家の評価、おすすめコースやセール情報まで詳しく解説!」
21万以上の講座があって、プログラミング、デザイン、ビジネススキル、マーケティング、データ分析…ほぼなんでも学べる。
しかも、買い切り型なのがポイント。
コンテンツは基本的に買い切り型です。そのため、一度購入すれば時間や費用を気にせず、自分のペースで繰り返し学習できます。
出典:エンジニアtype「【Udemyとは?】基本的な使い方から専門家の評価、おすすめコースやセール情報まで詳しく解説!」
NetflixやAmazon Primeみたいなサブスクじゃなくて、1講座ごとに買い切り。だから、「今月は見なかったのに料金払った…」みたいなことがない。
通勤中のスキマ時間でも見れるし、わからないところは何度でも見返せる。
講座動画は1本が数分から10分程度と短いものが多く、隙間時間に学べるようになっている。動画の再生スピードは0.5倍から2倍まで変えられるほか字幕機能もあり、自分のペースやスキルに合わせて学習できる。
どんなスキルを学べばいい?初心者向けおすすめジャンル
「で、何から始めればいいの?」って思うよね。
正直、これは人によるけど、社会人1年目におすすめなのはこの4つ。
1. プログラミング(Python、Web開発)
IT業界じゃなくても、プログラミングができると強い。データ分析とか、業務自動化とか、いろんなところで使える。特にPythonは初心者でも学びやすい。
Udemyは、スキルアップやキャリアチェンジを目指す幅広い層に利用されています。例えば、プログラミングを学んでWeb開発者になった人、デザインスキルを活かしてフリーランスになった人、あるいは趣味の音楽制作を始めた人など、Udemyでの学習を通じて目標を達成した事例は数多くあります。オンラインで手軽に学べるため、忙しい社会人でも自分のペースで学習を継続できるのが魅力です。
出典:エンジニアtype「【Udemyとは?】基本的な使い方から専門家の評価、おすすめコースやセール情報まで詳しく解説!」
2. Excel・データ分析
どの業界でも使う。営業でも、事務でも、企画でも。Excelが使えるだけで、仕事の効率が全然違う。上司に「おっ、こいつできるな」って思われる。
3. Webデザイン・動画編集
副業に直結しやすい。クラウドソーシングで案件取れるし、月3〜5万円稼ぐのは割と現実的。
4. ビジネススキル(営業、マーケティング)
今の仕事に直接活かせる。営業のコツとか、マーケティングの基礎とか、知ってるだけで差がつく。
正直、いくらかかるの?
「で、いくらかかるの?」が一番気になるよね。
通常価格は2,000円〜24,000円くらい。でも、月に2〜3回セールがある。
Udemyのセールは非常に頻繁に行われており、平均して月に2〜3回程度開催されています。大型セールは年に数回あります。
セール時なら、1,200円〜2,000円程度で買える。
1講座=飲み会1回分。
これで、転職できるスキルとか、副業で稼げるスキルが身につくなら、コスパ良すぎじゃない?
講座は1本ごとに購入する方式で、料金は無料から2万円程度まで様々。購入前にプレビューや受講者の評価を確認できるほか、30日返金保証もあり気軽に試せる環境が整っている。
30日間の返金保証もあるから、「合わなかったらどうしよう」って心配も不要だ。
まとめ:不安定な時代を生き抜くために、今日から始める「自分への投資」
今日から始める3ステップ
難しいことは言わない。まずはこの3つだけやってみてほしい。
STEP1:Udemyで興味のある講座を1つ探してみる
無料でプレビュー見れるから、「こんな感じか」ってイメージできる。 Udemy公式サイト
STEP2:セール情報をチェックする
メルマガ登録しとくと、セールの通知が来る。月2〜3回あるから、焦らなくて大丈夫。
STEP3:まずは1つ、講座を買って見てみる
飲み会1回我慢して、1,200円〜2,000円で1講座買ってみる。それだけ。
最後に:会社は守ってくれないけど、スキルは裏切らない
労働規制緩和で長時間労働が復活するかもしれない。 経済が不安定で、会社の業績が悪化するかもしれない。 転職したくても、スキルがなければ選べない。
会社は守ってくれないかもしれない。 政治も経済も不安定かもしれない。
でも、自分のスキルは誰にも奪えない資産になる。
社会人1年目のあなたには、まだ時間がある。
「まだ大丈夫」って思える今だからこそ、動くべきだ。
Udemyで1つ、講座を見てみよう。 それが、不安定な時代を生き抜く第一歩になる。

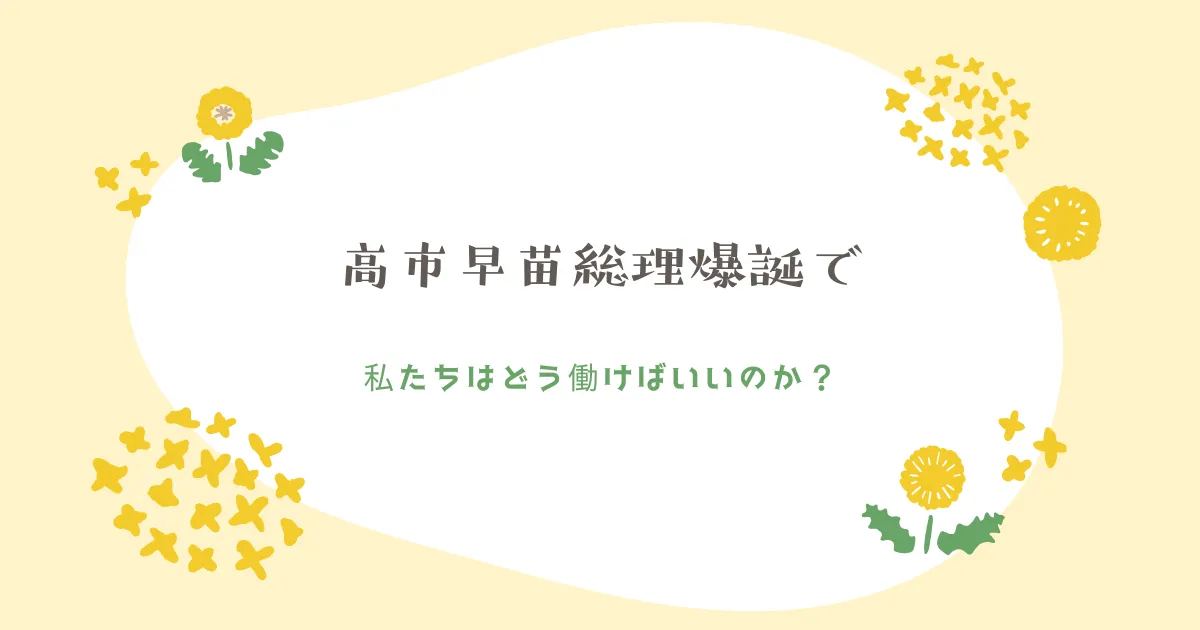


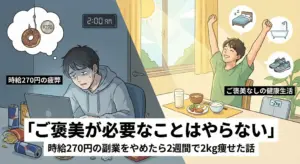


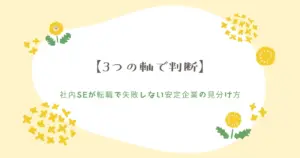
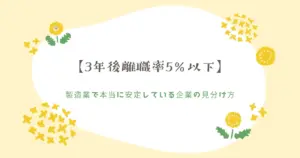
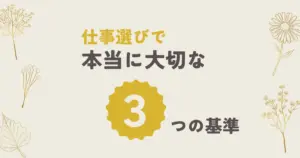
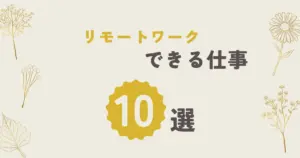
コメント