「やりたいこと、ある?」って聞かれて困ってない?
進路相談とか、将来の話になると必ず聞かれるこの質問。
「将来、やりたいことって何?」 「どんな仕事に就きたいの?」
正直、困りますよね。
だって、やりたいことなんて特にないし、仕事なんてぶっちゃけしたくない。今はゲーム実況見たり、アニメ見たりしてる方が楽しいし、将来のことなんて考えたくない…。
そう思ってるのは、君だけじゃありません。
大学進学者の40%が同じことで悩んでる
実は、大学に進学する人の40.1%が「将来やりたいと思う仕事が見つけられるか」という不安を抱えています。
受験校を選んだ時の不安や悩みについて聞くと、大学では「将来やりたいと思う仕事が見つけられるか」(40.1%)が、短期大学・専門学校では「授業についていけるか」(短期大学32.7%、専門学校39.8%)がトップとなった。
出典:マイナビ進学総合研究所「2024年 高校生の進路意識と進路選択に関する調査」
つまり、大学に行く人の約半数が、君と同じように「やりたいことが見つからない」って悩んでるんです。
これって、意外じゃないですか?
「みんなちゃんと将来のこと考えてて、自分だけが取り残されてる」なんて思ってたかもしれませんが、全然そんなことないんです。
正直、仕事なんてしたくないよね
もっと言うと、「仕事したくない」って思うのも、すごく普通のことです。
親や先生は「好きなこと、やりたいことをやりなさい」って言いますよね。
保護者が掛ける言葉としても「自分の好きなことをしなさい、やりたいことをやりなさい」(65.9%)が突出して高く、高校生の自主性を重んじる傾向が強い。
出典:リクルート「第11回 高校生と保護者の進路に関する意識調査2023」
でも、その「好きなこと」や「やりたいこと」が分からないから困ってるわけで。
むしろ今は、ゲーム実況見たり、面白いYouTube見たり、アニメ見たりしてる時間が一番楽しい。仕事なんて、できればしたくない。
この気持ち、すごく分かります。
だって、まだ働いたこともないのに「やりたい仕事」なんて想像できないですよね。
だからこの記事では、「やりたいこと」を無理に探すんじゃなくて、もっと現実的で、君にとって本当に役立つ仕事選びの基準をお伝えします。
なぜ「やりたいこと」が見つからないのか
そもそも経験が少ないから分からなくて当然
高校生の時点で「将来これがやりたい!」って明確に決まってる人の方が、実は少数派です。
実際、大学1年生の約31%が、高校卒業後も職業を意識したことがないというデータがあります。
大学1年生に、職業を意識した時期を聞いたところ、約31%が高等学校卒業以前に職業を意識することがない(「まだ考えていない」または「大学1年生」)と回答。
つまり、大学に入ってからも「まだ分からない」って人が3割もいるんです。
なぜこんなことが起きるかというと、**単純に「経験が少ないから」**です。
考えてみてください。君がこれまで直接体験した「仕事」って、ほとんどないですよね。
学校の先生、コンビニの店員さん、家族の仕事を少し聞いたことがあるくらい。
でも世の中には、何万種類もの仕事があります。
その中から「これがやりたい!」を見つけるなんて、正直無理ゲーです。
「やりたいこと」を探すのは、実は罠かもしれない
もっと言うと、「やりたいこと」にこだわりすぎるのは、逆効果かもしれません。
キャリア教育の現場では、**Will(やりたいこと)・Can(できること)・Must(すべきこと)**という3つの軸で仕事を考えるフレームワークがあります。
多くの人は「Will(やりたいこと)」から考えようとするんですが、実はこれが一番難しい。
なぜなら、やったことがないことは「やりたいかどうか」を判断できないから。
逆に、Can(できること)やMust(今すべきこと)から考えた方が、現実的で行動しやすいんです。
例えば:
- 「パソコンの操作は得意」(Can)
- 「人と話すのは苦手じゃない」(Can)
- 「とりあえず大学には行った方がいいかな」(Must)
こういう風に、「できること」や「やるべきこと」から逆算していくと、自然と選択肢が絞られてきます。
そして、実際に働き始めてから「あ、この仕事面白いかも」って思えることもあるんです。
つまり、「やりたいこと」は後からついてくることの方が多い。
無理に今見つけようとしなくても、大丈夫です。
じゃあ、何を基準に仕事を選べばいいの?
「やりたいこと」が見つからないなら、何を基準に仕事を選べばいいのか。
ここからは、実際に若い世代が重視しているポイントと、具体的な考え方を紹介します。
若者が実際に重視してる3つのポイント
大学生や若手社会人が「仕事選び」で重視しているのは、主にこの3つです。
1. ワークライフバランス(休日・残業時間)
「ワークライフバランス」という言葉が死語になるくらい、もはや仕事を選ぶ基準とも言えるようになりました。
出典:キャリアトレインブログ「ココがポイント!若者たちの仕事選び」
いくら好きな仕事でも、毎日残業で休みがなかったら続きません。
「楽しい生活をしたい」と考える新入社員が全体の40%を占めるというデータもあります。
つまり、仕事だけの人生じゃなくて、プライベートも大事にしたい。これが今の時代の普通です。
2. 人間関係(職場の雰囲気)
退職理由のランキング上位は、実は「人間関係」でほぼ埋め尽くされています。
1位 上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった 3位 同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった 6位 社長がワンマンだった
どんなに良い仕事でも、人間関係が最悪だったら地獄です。
逆に言えば、「この人たちとなら働けそう」って思える職場を見つけることが、すごく大事。
3. 給与・待遇(食べていける収入)
「食べていけるだけ稼げれば良い」という考え方の若者は少なくありません。
出典:キャリアトレインブログ「ココがポイント!若者たちの仕事選び」
「めちゃくちゃ稼ぎたい!」じゃなくても、最低限、生活できる給料は必要ですよね。
実際、マイナビの調査でも「給料が良い会社」を選ぶ人は年々増えています。
企業選択のポイントは「安定している会社」が49.9%で6年連続最多。「給料が良い会社」も3年連続で増加。
これらを見ると、「やりたいこと」よりも、「無理なく働ける環境」や「生活できる収入」の方が大事だと考える人が多いことが分かります。
「やりたいこと」より「やりたくないこと」を考える
もう一つ、すごく実用的な方法があります。
それは、消去法で考えること。
「やりたいこと」は分からなくても、「やりたくないこと」なら思い浮かびませんか?
例えば:
- 「営業で知らない人に電話するのは絶対嫌」
- 「ずっと座りっぱなしのデスクワークは無理」
- 「夜勤とかシフト制は避けたい」
- 「細かい作業をずっとやるのは苦手」
こういう風に、「これだけは嫌だ」をリストアップしてみてください。
やりたくないことが明確になれば、あとはそれが当てはまらない仕事を探すのみです。やりたいことがわからないという人はこのように消去法で見つけてくのも1つの手と言えるでしょう。
出典:就職エージェントneo「やりたい仕事や興味のある仕事がない」という就活生必見!
この方法なら、「やりたいこと」を無理に探さなくても、自分に合った仕事の方向性が見えてきます。
「できること」「興味があること」から逆算する
最後に、もう一つの視点を紹介します。
「やりたいこと」じゃなくて、「できること」や「ちょっと興味があること」から考える方法です。
例えば、君は今、暇な時間にゲーム実況動画やYouTube、アニメを見てますよね。
これって実は、**「映像コンテンツに興味がある」**ってことなんです。
そこから逆算すると:
- ゲーム実況が好き → 動画編集、配信技術、エンタメ業界
- アニメが好き → アニメ制作、声優、キャラクターデザイン、マーケティング
- YouTubeが好き → 企画制作、SNS運用、広告業界
こんな風に、「ちょっと興味あるかも」から仕事の選択肢を広げていくこともできます。
別に「YouTuberになれ」って言ってるわけじゃありません。
でも、君が時間を使ってることの中に、仕事のヒントは隠れてるんです。
「やりたいこと」は後からついてくる
仕事は「やってみて」初めて分かる
ここまで読んで、「でも、それでも何か決めなきゃいけないんでしょ?」って思うかもしれません。
その気持ち、分かります。
でも、実はZ世代(今の若い世代)の考え方は、少し変わってきています。
Z世代の75.1%が「自分の市場価値を上げたい」と考えている一方で、「自分のペースで成長したい」という回答は80.1%となり、「誰よりも早く成長したい」という回答の49.1%と大きな差が生まれている。
出典:SHIBUYA109 lab.「24卒・25卒に聞く!Z世代のキャリア観に関する意識調査」
つまり、「成長はしたいけど、自分のペースでいい」と考えてる人が多いんです。
これって、すごく現実的で健全な考え方だと思いませんか?
無理に「やりたいこと」を見つけて突っ走るんじゃなくて、少しずつ経験しながら、自分に合った道を探していく。
そういうスタンスでいいんです。
今できることは、自分に合った「環境」を見つけること
じゃあ、今の時点で何をすればいいのか。
それは、「自分に合った環境」を見つけるための情報収集と自己理解です。
実際、進路選択の満足度が高い学生には、ある共通点がありました。
進路を検討する際に「WEBサイトを調べる」よりも「自分の学びたいことを考えた・調べた」学生のほうが、進路選択への満足度が高い
出典:マイナビ進学総合研究所「2024年 高校生の進路意識と進路選択に関する調査」
つまり、ただ漠然とネットで学校を調べるんじゃなくて、「自分は何に興味があるのか」「どんな環境なら続けられそうか」を考えた人の方が、満足度が高いんです。
具体的には:
- オープンキャンパスに行ってみる(実際の雰囲気を感じる)
- 探究学習で自分の興味を深掘りする
- 「やりたくないこと」をリストアップする
- 家族や先生に、自分の強みを聞いてみる
こういう小さな行動が、将来の満足度に繋がります。
まとめ:焦らなくていい、自分のペースで考えよう
ここまで読んでくれて、ありがとうございます。
最後にもう一度、大事なことをまとめます。
「やりたいこと」が見つからないのは、全然おかしいことじゃありません。
大学進学者の40%が同じ悩みを抱えてるし、大学に入ってからも「まだ分からない」って人が3割もいます。
だから、焦らなくて大丈夫。
仕事選びは、「やりたいこと」じゃなくて、こんな基準で考えてもいいんです:
- ワークライフバランス(無理なく働けるか)
- 人間関係(一緒に働く人は大丈夫そうか)
- 給与・待遇(生活できる収入があるか)
- 消去法(やりたくないことを避ける)
- できること・興味があること(今の自分から逆算する)
そして、「やりたいこと」は後からついてくることの方が多い。
今は、自分に合った環境を見つけるための情報収集と、自己理解を深める時期です。
君は今、ゲーム実況やアニメを見るのが好きなんですよね。
それも立派な「興味」です。
そこから、「映像が好きなのかな」「エンタメに興味があるのかな」って考えてみるだけでも、十分最初の一歩になります。
焦らず、自分のペースで。
「やりたいこと」を無理に見つけようとしなくても、ちゃんと道は開けます。
まずは、今日から少しだけ、自分のことを考えてみませんか?

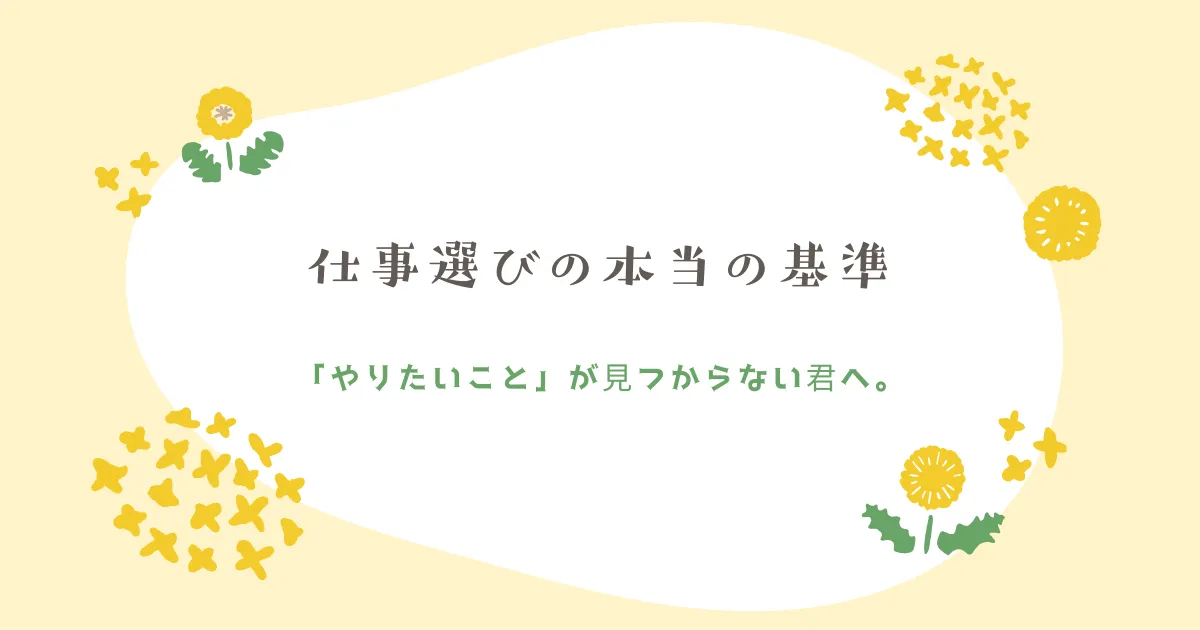


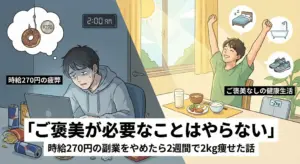


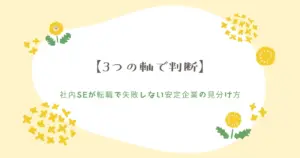
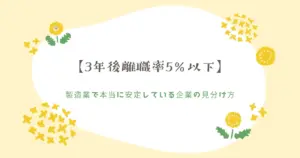
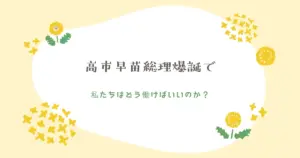
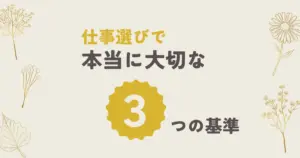
コメント