「将来やりたいことがわからない」って、普通のことです
この記事を読んでいるあなたは、おそらく「将来どうしよう」と漠然とした不安を抱えているんじゃないでしょうか。
勉強もそこまで得意じゃない。やりたいことも特にない。暇な時間はゲーム実況やYouTubeを見て過ごしている。友達もそんなに多くないし、部活もやってない。
「こんな自分で大丈夫なのかな…」
そんな風に思っているかもしれません。でも、安心してください。あなただけじゃないんです。
ソニー生命保険が2025年に実施した調査によると、高校生の46%が「10年後は不安」と回答しています。つまり、クラスの半分くらいが同じように不安を感じているということです。
自身の将来(1年後、3年後、10年後)について、明るい見通しをもっているか、不安を抱いているかを聞いたところ、高校生は「10年後」明るい(計)54.0%、不安(計)46.0%となりました。
この記事では、「将来が不安」なあなたが、その不安を少しずつ行動に変えていくための3つのステップを紹介します。完璧な答えを出す必要はありません。ただ、小さな一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
なぜ「将来が不安」なのか?
まず、なぜ私たちは将来に不安を感じるんでしょうか。
2025年6月に実施された高校生への調査では、最も多かった回答は「お金・物価の問題(収入や生活費など)」で60.5%。次いで「就職できるかどうか」(50%)、「働き方(ブラック企業、長時間労働など)」(45.4%)という結果でした。
「将来に不安を感じていること」を聞いたところ、最も多かった回答は「お金・物価の問題(収入や生活費など)」で60.5%。次いで「就職できるかどうか」(50%)、「働き方(ブラック企業、長時間労働など)」(45.4%)と続き、経済的な将来不安が高校生にも強く影を落としていることが明らかになりました。
でも、もっと根本的な悩みもあります。文部科学省の調査では、「自分に合っているものがわからない」「やりたいことが見つからない、わからない」「社会に出て行く能力があるか自信がない」という悩みが多いことが分かっています。
高校生に進路選択に関する気掛かりを尋ねたところ、「自分に合っているものがわからない」「やりたいことが見つからない、わからない」「社会に出て行く能力があるか自身がない」という者が多い
つまり、不安の正体は**「情報不足」と「経験不足」**なんです。どんな仕事があるのか、自分に何が向いているのか、そもそも自分が何をしたいのか。それが分からないから不安なんですよね。
逆に言えば、少しずつ情報を集めて、小さく試してみれば、不安は少しずつ小さくなっていくということです。
STEP1:今の自分を「見える化」する【所要時間:15分】
不安を行動に変える最初のステップは、今の自分を知ることです。
「自己分析」とか言うと難しそうに聞こえますが、要は「自分って何が好きで、何が嫌いなんだっけ?」を整理するだけです。紙とペン(スマホのメモでもOK)があればできます。
自分史で過去を振り返ってみる
「自分史」とは、自分の過去を時系列に沿って振り返る手法です。難しく考えなくて大丈夫。ざっくりでいいんです。
例えば、こんな感じで書き出してみてください:
小学生の頃
- 楽しかったこと:友達とゲームで遊んだこと、図工の時間
- 嫌だったこと:運動会、人前で発表すること
中学生の頃
- 楽しかったこと:YouTubeでゲーム実況を見ること、好きなアニメの話を友達とすること
- 嫌だったこと:部活の人間関係、テスト勉強
高校生の今
- 楽しいこと:ゲーム実況やアニメを見ること、のんびりする時間
- 嫌なこと:将来のことを考えること(笑)、朝早く起きること
これを書き出すだけで、自分が何を大切にしているかが少し見えてきます。例えば「人前に出るのは苦手だけど、一人で楽しめることは好き」とか。
好きなこと・嫌いなことリストを作る
次に、もう少し具体的に「好き」と「嫌い」を書き出してみましょう。
ここでポイントなのは、**YouTubeで何を見ているか?**です。あなたが毎日見ているコンテンツには、実はあなたの興味が詰まっています。
例えば:
- ゲーム実況が好き → どんなゲーム?ホラー?RPG?FPS?
- 解説系の動画が好き → 誰かが教えてくれる動画に興味がある?
- Vtuberが好き → キャラクターや声に興味がある?それともトーク力?
「ホラーゲームの実況は見るけど、自分ではプレイしたくない」なら、それは**「観察する側が好き」なのかもしれません。逆に「自分でもやってみたい」なら、「体験する側が好き」**かもしれない。
こういう小さな違いが、実は将来の仕事選びのヒントになったりします。
オンラインツールで客観的に分析
自分で考えるのが難しければ、ツールを使ってみるのもアリです。
高校生新卒のための就活情報サイト「U:story」では、たった10個の質問に答えるだけで客観的な視点で分析してくれる適性検査が受けられます。
高校生新卒のための就活情報サイト、U:storyでは適性検査を受けられます。たった10個の質問に答えるだけで、客観的な視点で分析してくれます。
完璧な答えが出るわけじゃないですが、「へー、自分ってこういう傾向があるんだ」くらいの参考にはなります。
STEP2:小さく「試してみる」【できることから1つだけ】
自分のことが少し分かったら、次は小さく試してみるステップです。
ここで大事なのは、「完璧にやろう」と思わないこと。まずは気軽に、できることから1つだけやってみましょう。
友達と「将来の話」をしてみる
一番簡単なのは、友達と「将来どうする?」って話してみることです。
同じ時代を生きている同級生に聞くことで、今悩んでいる将来への不安をなくすきっかけを作ることもできるんですよね。
将来について大人に相談する人もいますが、時代は変化し、働き方や生き方への考え方も変わってきます。なので同じ時代を生きている同級生に聞くことで、今悩んでいる将来への不安をなくすきっかけを作ることもできるでしょう。
LINEで「お前、将来どうすんの?」って聞くだけでもOK。意外と「俺も決まってないわ」って返ってきたりします。それだけで「自分だけじゃないんだ」って安心できたりするもんです。
興味ある分野を「5分だけ」調べる
次に、YouTubeで見ている動画の職業について、5分だけ調べてみてください。
例えば:
- 「ゲーム実況者になるには」
- 「動画編集の仕事」
- 「声優ってどうやってなるの」
完璧な情報収集をする必要はありません。ググって上位3つくらいの記事をパラパラ見るだけでOK。「へー、そうなんだ」くらいの感覚で十分です。
オープンキャンパスや説明会に(気軽に)行ってみる
もし少しでも時間があるなら、大学や専門学校のオープンキャンパスに行ってみるのもおすすめです。
志望大や学びたい学問が決まっていない高校生こそ、大学のオープンキャンパスへ積極的に参加するのがおすすめです。
志望大や学びたい学問が決まっていない高校生こそ、大学のオープンキャンパスへ積極的に参加するのがおすすめです。少しでも興味のある大学や、とりあえず知っている大学でもOKです。
「とりあえず知っている大学」でもいいし、友達と一緒に行ってもいい。「雰囲気だけ見に行く」くらいの気持ちでOKです。行ってみたら「こんな学部があるんだ」「意外と楽しそうかも」って思えることもあります。
STEP3:「続けられる」仕組みを作る
最後のステップは、続けられる仕組みを作ることです。
一度やっただけで終わらせないために、ちょっとした工夫をしておくと楽です。
週に1回、15分だけ「将来のことを考える時間」を作る
スマホのリマインダーで、**毎週日曜日の夜21時に「将来のこと考える」**みたいな通知を設定してみてください。
15分だけでいいです。その時間に、今週見つけたことや、気になったことをスマホのメモに残しておく。それだけで、少しずつ自分の中で情報が整理されていきます。
「失敗してもOK」のマインドを持つ
あと、これめちゃくちゃ大事なんですが、**「失敗してもOK」**って思っておいてください。
実は、Yahoo!知恵袋のあるベストアンサーにこんな意見がありました。
ちなみに高校生の時点で将来のことを決めてるなんて、子供でも目にする職業か親の影響に偏るはずです。で、たいていは「やっぱり違う」と進路変更します。ヘタに専門的な学校とかに行ってから進路変更するのは本当に大変ですよ。
つまり、高校生の時点で将来のことを決めている人は少なく、大半は「やっぱり違う」と進路変更するんです。
だから、今の段階で「これだ!」って決める必要はないし、試してみて「なんか違うな」って思ったら、また別のことを試せばいいだけです。
進捗を「誰かに話す」
最後に、考えたことや試したことを誰かに話すのもおすすめです。
親でも、友達でも、先生でも誰でもOK。話すことで自分の考えが整理されるし、他己分析で客観的な視点を取り入れることで自己理解が深まることもあります。
他己分析をおこなうメリットは、自分の強みや弱みを知る過程で客観的な視点を取り入れられることです。自身と他者の理解が合っている部分には説得力を持たせられますし、理解が合っていない場合には、そのギャップを埋めるためにとるべき行動が明確になります。
「最近、将来のこと考えてるんだけどさ」って話してみるだけでも、意外と相手が「俺もそうだよ」とか「こんな話聞いたよ」って返してくれたりします。
まとめ:不安は「行動」で小さくなる
ここまで読んでくれてありがとうございます。
正直、この記事を読んだだけで「将来の不安が完全に消えた!」とはならないと思います。でも、小さな一歩を踏み出すきっかけにはなったんじゃないでしょうか。
最後にもう一度、3つのステップをおさらいします:
- 今の自分を「見える化」する(自分史、好き嫌いリスト、ツール活用)
- 小さく「試してみる」(友達と話す、5分調べる、オープンキャンパス)
- 「続けられる」仕組みを作る(週1回15分、失敗OK、誰かに話す)
不安を感じているのは、あなたが真面目に将来のことを考えている証拠です。それ自体、すごくいいことだと思います。
完璧な答えを求めなくていい。まずは**「今日できること」を1つだけやってみる**。それだけで、不安は少しずつ行動に変わっていきます。
この記事が、あなたの小さな一歩のきっかけになれば嬉しいです。



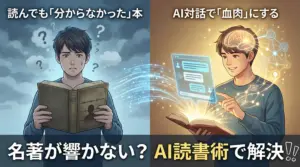

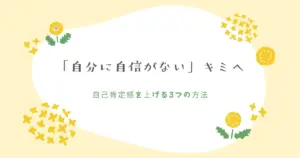
コメント