「将来やりたいことって、何?」
友達や先生にそう聞かれて、困ったことはないだろうか。正直、将来のことなんて考えてもよくわからないし、勉強もそこまでできるわけじゃない。暇な時間はゲーム実況動画を見たり、面白いYouTubeやアニメを観て過ごしている。「このままでいいのかな」って漠然とした不安はあるけど、じゃあ何をすればいいのかもわからない。
そんなキミは、決して一人じゃない。
全国の高校生310人に「進路について悩んでいますか?」と聞いたところ、71.3%が「はい」と答えた。なかでも多かったのが、「将来やりたいことがわからない」という悩み。
出典:将来何がしたいかわからない高校生へ!やりたいことのみつけ方|スタディサプリ進路
実は、7割以上の高校生が同じように悩んでいる。キミだけじゃないんだ。
この記事では、「自分に自信がない」と感じているキミに向けて、自己肯定感を上げる3つの方法を紹介する。なぜ自己肯定感なのかというと、自分を認められるようになると、不思議と「やってみようかな」と思えることが増えてくるから。進路を決める第一歩は、実は「自分はこれでいいんだ」と思えることだったりする。
難しいことは言わない。今日から少しずつ試せることを、一緒に見ていこう。
そもそも「自己肯定感」って何?【高校生向け解説】
「自己肯定感」って言葉、最近よく聞くようになったけど、正直ピンとこない人も多いんじゃないだろうか。
簡単に言うと、こういうことだ。
自己肯定感とは、「自分はこれでいいのだ」と無条件で自分を肯定する感覚のこと。条件を何もつけないのがポイントです。「成績が良いから」「友達が多いから」といった条件をいっさいつけなくても、「自分はこのままでいい」「存在しているだけで価値がある」と思える人は、自己肯定感が高いと言えます。
つまり、「テストで90点取ったから自分はすごい」じゃなくて、「テストの点数関係なく、自分は自分でいいんだ」と思える感覚のこと。
ここで一つ、知っておいてほしいデータがある。
高校生は、自分で自分を作る「自立」の総仕上げの時期なので、自己肯定感が不安定になりがちです。小学生のころは「自分は何でもできる」という万能感が強い傾向がありますが、思春期になると、自己形成をするにあたって自信がゆれて、「自分はこれでいいのだ」と思えたり、やっぱり他人の意見を気にしたりと、不安定になるのが普通です。
高校生の時期に自己肯定感が揺れるのは、実は当たり前のこと。「自分だけがこんなに悩んでる…」と思う必要はない。みんな、多かれ少なかれ同じように揺れている。
もう一つ、日本人全体のデータも見てみよう。
国立青少年教育振興機構の調査では、「自分はだめな人間だと思うことがある」という質問に、日本人の72.5%が「とてもそう思う」「まあそう思う」と回答しています。
出典:自己肯定感を高める方法とは|WEBCAMP MEDIA
7割以上だ。つまり、10人いたら7人は「自分ダメだな」って思ったことがあるってこと。キミが「自分に自信がない」と感じているなら、それはむしろ普通のことなんだ。
自己肯定感が低いと、なぜ進路が決まらないの?
じゃあ、自己肯定感が低いと、なぜ進路選びで困るのか。
理由は単純で、「どうせ自分には無理」と思ってしまうから。
例えば、こんな経験はないだろうか。
- 「この大学面白そうだな」と思っても、「自分の成績じゃ無理だろうな」と諦める
- 「この仕事かっこいいな」と思っても、「自分には才能ないし」と最初から選択肢から外す
- 友達が「将来はこれやりたい」って話してるのを聞いて、「自分だけ何も決まってない…」と焦る
自己肯定感が低いと、こんなふうに自分で自分の可能性を狭めてしまう。
実は、こういう悩みを持っている高校生はめちゃくちゃ多い。
高校生に進路選択に関する気掛かりを尋ねたところ、「自分に合っているものがわからない」「やりたいことが見つからない、わからない」「社会に出て行く能力があるか自身がない」という者が多い
出典:進路を考える時、高校生はどんな気持ちになるか|文部科学省
「自分に合っているものがわからない」「やりたいことが見つからない」――これ、全部つながっている。自己肯定感が低いと、「自分には何が合ってるんだろう?」って考えること自体が怖くなるんだよね。
でも、ここで一つ大事なことを言っておきたい。
なりたい職業や将来やりたいことは、知っていることのなかでしか生まれないからです。高校生のうちから仕事について知っていることは限られているはず。
つまり、「やりたいことがない」のは当たり前。だって、まだ世の中のことをそんなに知らないから。知らないものの中から選ぶなんて、できるわけがない。
だから、まずやるべきことは「やりたいことを無理に見つけること」じゃなくて、「自分はこれでいいんだ」と思えるようになること。自己肯定感が上がると、「よし、ちょっと調べてみるか」「これ試してみようかな」って思えるようになる。そこから、少しずつ進路が見えてくる。
【方法①】小さな成功体験を積み重ねる
さて、ここからは具体的な方法を3つ紹介していく。
まず一つ目は、小さな成功体験を積み重ねること。
「成功体験」って聞くと、「テストで100点取る」とか「部活で優勝する」とか、大きなことをイメージするかもしれない。でも、そういうことじゃない。もっと小さくていい。
大きな成功体験1つよりも、小さな成功体験が10個あるほうが、「自分っていいな」と自信が持てるようになります。たとえば「めんどくさい上司に自分から挨拶しよう」ということでも十分です。トライしてうまくいったことならなんでも成功体験だと思ってください。
出典:自己肯定感が低く自信がない人がすべき「成功体験」の積み方|ゴールドオンライン
「大きな成功1回」より「小さな成功10回」。これが大事。
具体的にどんなことをすればいいのか。例えば、こんな感じだ。
- 毎日決まった時間に起きる(例:平日は7時に起きる、と決めて1週間続ける)
- やることリストを作って、できたことにチェックをつける
- 好きなゲームやアニメについて、誰かに1つ説明してみる(友達でも家族でもいい)
- YouTubeで見た面白いことを、誰かに話してみる
こういう小さなことでいい。
ちなみに、「やることリストにチェックをつける」っていうのは、実際に高校生がやってる方法だ。
やることリストを作って、できたことにはチェックする。自分がきちんと進められていることを自覚しやすくなると思う。チェックをつけるたびに「自分結構できてるじゃん」と自分を褒めます。
出典:自己肯定感を上げるために高校生が実践する10の方法|高校生新聞オンライン
「自分結構できてるじゃん」って思えること。これが自己肯定感を上げる第一歩。
なぜこれが効果的なのかというと、心理学的な裏付けがある。
心理学者のアルバート・バンデューラは、「自己効力感理論」の中で、自分にはできるという信念(自己効力感)が、自尊感情に大きな影響を与えると述べています。自己肯定感の向上にも、大きく関係しています。
つまり、「自分にはできる」って思える経験を増やすことが、そのまま自己肯定感を上げることにつながる。
大事なのは、「できたこと」を見逃さないこと。多くの人は、できなかったことばかり数えてしまう。でも、できたことに目を向ける。それだけで、少しずつ変わっていく。
【方法②】マイナス思考をプラスに言い換える練習
二つ目の方法は、マイナス思考をプラスに言い換える練習。
例えば、こんなふうに。
マイナスなことをプラスに言い換える練習をしましょう。例えば新しいことに挑戦するとき、「自分は臆病だから無理」ではなく、「自分は慎重な性格だからすぐには行動しないのだ」と思えたら前向きに考えられますよね。「人の目が気になる」と思うより、「相手の気持ちを常に考えている」と言い換えれば、行動も変わってくるはずです。
これ、最初は「そんな都合よく考えられないよ」って思うかもしれない。でも、実は長所と短所って表裏一体なんだ。
長所と短所は表裏なので、「気が短い」という短所は「すぐ行動に移せる」という長所でもあります。ネガティブなことをポジティブに考え、欠点だと思いがちなことを良いことに言い換える練習をすると、自己肯定感も高まっていくと思います。
例えば、この記事を読んでいるキミが「勉強があまりできない」「やりたいことがない」「帰宅部でインドア」だとしたら、こんなふうに言い換えられる。
- 「勉強できない」→「今は得意分野を見つける途中」
- 「やりたいことがない」→「色んな可能性が開いている」「固定観念にとらわれていない」
- 「帰宅部でインドア」→「自分の時間を大切にできる」「一人の時間を楽しめる」
ゲーム実況動画やYouTube、アニメを見るのが好きなら、それは「人を楽しませることに興味がある」ってことかもしれないし、「クリエイティブなものが好き」ってことかもしれない。
ちなみに、どうしてもネガティブ思考が止まらないときは、こんな方法もある。
マイナスなことを考え続けてしまったら、ヒザや手をポンッと軽く叩いて、「もう考えるのやめた」と声に出しましょう。失敗したことやネガティブなことを一人で考え始めると、ぐるぐる思考といって、いつまでも頭から離れず、どんどん視野が狭くなって、悪いほうに考えてしまい解決方法が出てこなくなります。
膝や手を叩いて、「もう考えるのやめた!」って声に出す。これ、意外と効く。騙されたと思って一回やってみてほしい。
【方法③】「やりたくないこと」から考えてみる
三つ目の方法は、ちょっと視点を変えて、「やりたくないこと」から考えてみること。
「やりたいこと」って聞かれると困るけど、「やりたくないこと」なら意外とすぐ出てくる。
もし、夢や自分のやりたいことが浮かばない場合は、「やりたくない」ことについて考えてみます。「単純作業の継続が苦手」「人前に出るのはひどく緊張する」「数字に弱い」など、苦手なことや絶対に避けたいということならば比較的すぐに浮かんでくるのではないでしょうか。
そして、ここが大事なポイント。
自分にとっての「やりたくないこと」を把握しておけば、おのずと向いている仕事ややってみたい仕事が導き出せるはずです。
例えば、キミがゲーム実況動画やYouTubeをよく見ているなら、こんなふうに考えられる。
- ゲーム実況やYouTubeが好き→**「人を楽しませることが嫌いじゃない」**かも
- インドアが好き→**「外回りより内勤が向いてる」**かも
- アニメが好き→**「クリエイティブな分野に興味がある」**かも
逆に、「やりたくないこと」を考えてみると:
- 「毎日満員電車に乗って通勤するのは嫌だな」→リモートワークができる仕事がいいかも
- 「ずっと立ちっぱなしの仕事は疲れそう」→デスクワーク中心の仕事が向いてるかも
- 「人前でプレゼンとかは緊張する」→裏方の仕事の方が得意かも
こんなふうに、「やりたくないこと」から逆算すると、意外と「自分に合ってること」が見えてくる。
そして、ここで大事なのは、**「動きながら考える」**こと。
「動きながら考える」ことが、高校生活のなかでやりたいことをみつけるポイントになる。例えば ・オープンキャンパスに参加する ・進路相談会で情報収集する ・まわりの人たちの意見を聞く ・適職診断ツールで自分の傾向を知る など。
出典:将来何がしたいかわからない高校生へ!|スタディサプリ進路
頭の中でずっと考えてても答えは出ない。だから、小さくていいから行動してみる。オープンキャンパスに行ってみる、適職診断やってみる、先生に相談してみる。そういう小さな一歩が、進路を決めるヒントになる。
自己肯定感が上がると、進路選択が変わる理由
ここまで3つの方法を紹介してきた。
- 小さな成功体験を積み重ねる
- マイナス思考をプラスに言い換える
- 「やりたくないこと」から考えてみる
じゃあ、自己肯定感が上がると、具体的にどう変わるのか。
まず、こんな考え方ができるようになる。
思い切って言ってしまえば、これは高校生ならば当たり前のことです。高校生時点での選択がその後すべてに影響するわけでもなく、卒業後に舵を切る時間は十分あります。将来が見えないことを、そこまで不安がる必要はありません。
「今決めたことが全てじゃない」って思えるようになる。これめちゃくちゃ大事。
もう一つ、これも知っておいてほしい。
高校生や大学生のうちに一生の仕事を決める必要はありません。これから先、会社を決める前に仕事を体験する機会があります。社会人になってから、経験を重ねるなかで、自分の向き不向きに気づくこともあります。職種を変える、仕事を変える、会社を変える機会もあります。
つまり、今完璧な答えを出さなくていい。むしろ、今は「これ面白そうだな」「ちょっと調べてみようかな」って思えることが大事。
自己肯定感が上がると、こんな変化が起きる:
- 「やってみようかな」と思える(失敗を恐れすぎなくなる)
- 自分の意見を持てるようになる(周りに流されにくくなる)
- 「まあ、なんとかなるか」と思える(完璧主義から解放される)
そして、進路選びも、焦らずに進められるようになる。
早いうちから話し合いを重ねて、納得できる進路を一緒に見つけられるとよいですね。
出典:進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと|ベネッセ教育情報サイト
親や先生と相談しながら、ゆっくり決めていけばいい。
まとめ:完璧じゃなくていい。小さな一歩から始めよう
ここまで読んでくれて、ありがとう。
最後にもう一度、3つの方法をおさらいしておこう。
- 小さな成功体験を積み重ねる(やることリストを作って、できたことをチェック)
- マイナス思考をプラスに言い換える(短所は長所の裏返し)
- 「やりたくないこと」から考えてみる(逆算して自分に合うことを見つける)
どれも、今日からできることばかり。
高校生のうちは、「こんな仕事っておもしろそうだな」「この仕事の働きがいって何だろう?」など、興味をもって情報収集することが一番大切です。
完璧な答えを出そうとしなくていい。「これ面白そうだな」って思えることを、少しずつ増やしていけばいい。
もし、「やっぱり一人じゃ不安だな」と思ったら、進路相談やオープンキャンパスに参加してみるのもいい。先生や親に相談してみるのもいい。一人で抱え込まなくていい。
「自分に自信がない」っていうのは、実は「成長の途中」ってこと。今のキミは、これから変わっていける。だから、焦らなくていい。
まずは、今日できる小さなこと一つから始めてみよう。



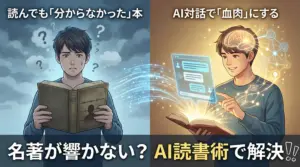

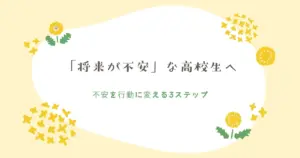
コメント